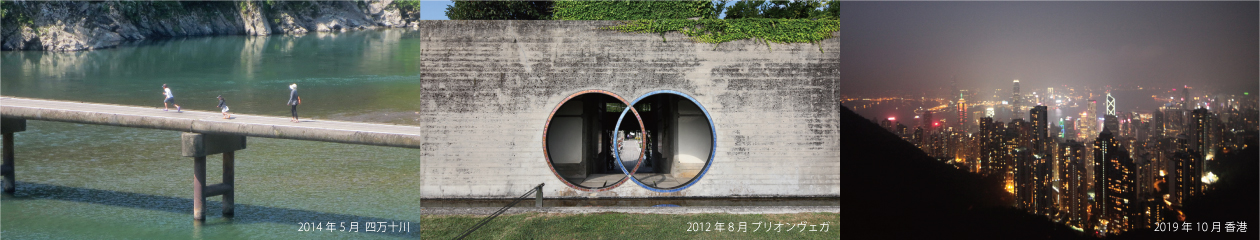昨日、関西万博が開幕しました。
それを記念して、ブルーインパルスが大阪城上空を2回通過するとのこと。
近所の方も、難波宮跡公園へ向かっているようです。

予定時刻は11時50分と、11時56分。
時刻が近付くにつれて、雨がやや強くなってきましたが、「関空を離陸したよ」という声も聞こえてきました。

ワクワクして待っていると、今度は「中止になったみたい」と。
徐々に、皆が帰路についたのです。
大阪では35年振りと聞いていたので残念です。また機会を作って貰えると嬉しいのですが。

直前まで、万博の盛りあがりをあまり感じていませんでした。
しかし、折角の地元開催なので前売チケットを買ったのは先週のこと。
高島屋東別館で「EXPO 博覧会の時代」という企画展があると知り、のぞいてみました。

難波の大阪高島屋から言えば、南西にあたる堺筋沿いにあります。

エントランスも立派。
2020年にリノベーションし、2021年には国の重要文化財に指定されています。

タイトルからすると「博覧会の時代」と言われた、1990年代の万博の歴史を紐解く内容を想像していました。

しかしここは高島屋資料館なので、高島屋が出品した室内装飾品などの展示がメインでした。
考えてみれば当たり前ですが、こちらが万博モード過ぎていたようです。

それでも、万博に関する資料もいくつかありました。
第1回目は1851年、ロンドン万博ですが、最も知られているのは1889年のパリ万博ではないでしょうか。
フランス革命100周年を記念し、開催にあわせて完成したエッフェル塔は、現在でもパリのシンボルです。
資料には、エジソンの蓄音機が大変な人気を博したとあります。万博の果たした役割がうかがい知れます。
また、1970年の前回大阪万博では、お祭り広場と太陽の塔がシンボルとなりました。
どちらにおいても、建築は主役的な役割を担ってきました。
1970年生まれの私は、この万博が開催中に55歳になります。
建築家としても十分キャリアを積んできたつもりですが、今回の万博に全く関われなかったのはとても残念です。
大小さまざまなコンペがあったのですが、何一つ参加できていないので当然と言えば当然ですが、それでも忸怩たる思いがあるのは間違いありません。
公共建築で指名を受けたければ、実績を積み重ねていくしかないので、ひとつずつの仕事で結果を残していくしかありません。アトリエ移転もきっかけとして、ギアを上げて行きたいと思います。

高島屋東別館があるあたりは、でんでんタウンと呼ばれ、家電量販店、電気部品店等が並びますが、現在は「オタロード」なる名前も付加されています。
アニメ、フィギュア、同人誌を扱う店が多くあり、「西の秋葉原」とも言われているのです。

以前とは全く風景が変わり、メイド喫茶も沢山あります。

その店員さんが道に並んで、店の案内?客引き?をしていました。
私が学生の頃は、オーディオオタク、家電オタクが集まる場所というイメージでしたが、時代が変わればこれだけ変わるのです。
加えて言うなら、これだけ情報があふれていると、「観る」というアトラクションでは、刺激が足りないのだと思います。
USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)にしても、メイド喫茶にしても体験型です。
そう考えると、 「博覧会の時代」と言われた、1990年代後の万博は、なかなか難しいものがあると思います。

日本橋と難波の境目あたりにある、焼売(シュウマイ)の名店「一芳亭」。
黄色い皮の焼売(シュウマイ) は、美味しくかつリーズナブル。
長らく行っていないので、帰りに前を通ってみました。
体験型アトラクションの最たるものは、やはり「食べる」につきるでしょう。
向いにあるメイド喫茶には長蛇の列ができていました。
金額もそれなりだったので、時代を感じずにはいられなかったのです。
■■■2月12日(水)大阪市中央区上町1-24-6に移転しました
「上町のアトリエ付き住宅〈リノベーション〉」
電話、faxは変更ありません■■■
■9月17日(火)「尼崎園田えぐち内科・内視鏡クリニック」開業■
■8月30日『homify』の特集記事に「阿倍野の長屋<リノベーション>」掲載■