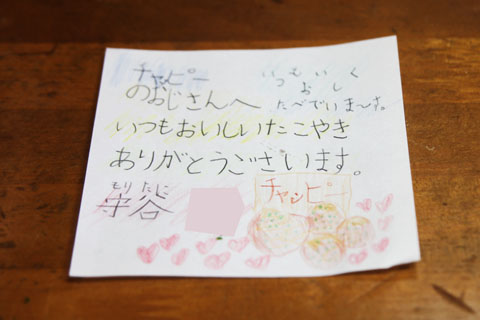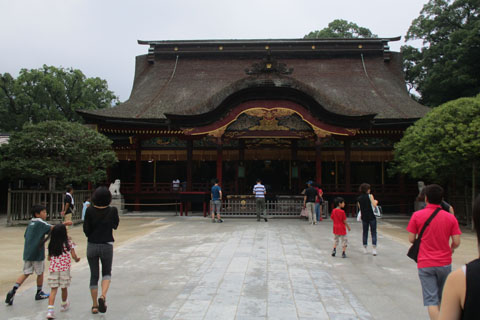終戦から72年。
戦争を、20代、30代で体験した祖父母は、すでに4人とも亡くなってしまいました。
終戦時に8歳だった人が現在80歳。戦争体験を聞く機会は、この10年でほぼ無くなってしまいます。
2月11日、12日と初めて沖縄を訪れましたが、戦争についてはやはり素通りできないと思っていました。

那覇の目貫通りは国際通り。
夕方だけなのか、歩行者天国になっていました。

ある交差点では、ストリートパフォーマンスをしている若者がいます。
平和な日曜午後の風景です。
後ろに見えるのは安売りのドン・キホーテ。
この建物は安藤忠雄の設計で、もとの名は「フェスティバル」だったと思います。
今はベージュのペンキが塗られ、打ち放しの見る影もありません。しかしそれも時代の流れです。

ここに書くのはあくまで私の歴史観、戦争観です。
2ヶ所だけですが、沖縄戦の痕跡を訪ねてきました。
旧海軍司令部豪は那覇市街を見下ろす、小高い山にあります。
アメリカ軍の砲撃に耐えるため、山をくり抜いて作られた地下陣地でした。

450mあったうちの300mが公開されていました。

ここは司令官室。
漆喰が施されています。

ここは下士官兵員室。
スリット状に影が見える部分に、元は木の支柱がありました。
下士官は、立錐の余地なく立ったまま眠ったそうです。
ツルハシの跡が生々しく残るこの空間で、立ったまま眠り、戦に勝てる訳などありません。

そして幕僚室。
壁に残るのは幕僚が手榴弾で自決した際、飛び散った破片の跡です。
生々しく残るその跡を、正直、真正面から見ることは出来ませんでした。
責任は自決してとる。
その場にいればそれが正しいと私も思ったかもしれませんが、どんなことがあっても生きてこそです。
それを分からなくするのが戦争でしょうか。

もう1ヶ所は糸数アブチラガマ。
那覇から南東へ10km程いった小高い丘の中腹にあります。

先の戦争で、沖縄への上陸は本島中部、読谷村(よみたんそん)あたりから開始されました。
アメリカ軍は徐々に南下してきたため、本島南部は最終の激戦地となりました。

「ガマ」とは沖縄方言で、洞窟やくぼみを指します。
「アブ」は深い、「チラ」は崖をさします。深い、深い、とても暗い洞窟でした。
以前は撮影を許可していたそうですが、現在はガマの手前まで。やはりネット社会は難しとのことでした。
内部には照明はなく、懐中電灯を手に1時間程かけて案内をしてくれます。
この糸数アブチラガマは、もとは集落の非難指定豪だったのが、陣地豪となり、病院の分室となりました。
病院分室となってからは、ひめゆり学徒もこの地に配備され、負傷兵の治療にあたります。
トイレなどないので、糞尿を一斗缶に入れ、夜の間にガマの外へ捨てに行くのも彼女達の仕事だったそうです。
衛生状態が悪いので、負傷兵の手や足が切断されたものも、彼女たちが外部へ捨てにいきました。
人はそんな悲惨な日常にも慣れてしまうそうで、高校生くらいのひめゆり学徒も「これ○○さんの足だから、重くてかなわないね」とような会話を交わすようになっていったのです。
人が人でなくなる。それが戦争なのではないでしょうか、とガイドの方が言っていました。
最終的に軍からの撤退命令がでると、歩けない負傷兵と地元の人だけがここに残りました。
アメリカ軍は入り口からガソリンを流し込み、火を放ちましたが、湿気が多い為全体へは広がらなかったそうです。
それでも、ガマ内の天井は黒く焦げ、爆発したドラム缶の一部が、濡れた紙のように天井にへばりついていました。

それはこの出口からすぐそこで起こったこと。地元の方の何人かが、そこで命を落としたのです。

本土決戦に備える時間稼ぎのために「沖縄は捨て石にされた」と糸数アブチラガマのwebサイトにはあります。
更にこうあります。
沖縄戦で、日本兵6万6千人、沖縄出身兵2万8千人、米兵1万2干人、一般住民9万4千人が亡くなりました。
当時の沖縄県の人口は約50万人でしたから、沖縄県民の4人に1人が亡くなったことになります。

日本で唯一、地上戦を経験した沖縄。
アメリカ軍、日本軍、沖縄県民が入り乱れた、終戦間際は地獄絵図だったといいます。
スパイを疑われ、殺された県民もいたとのことでした。
沖縄戦で亡くなった日本軍の中で、沖縄の次に多かった出身地は、北海道だそうです。
ガイドの方が「内地という言葉があるとおり、やはり沖縄、北海道など、地方の貧しい人達の多くが命を落としたのかもしれません」と言っておられました。
大阪に住んでいて、「内地」という言葉を使うことはありません。
その音には、ある種の不公平感が含まれていることを、私達は認識しなければなりません。

サトウキビ畑の中にぽっかりと空いた、糸数アブチラガマ。
案内の途中で「いちど全て懐中電灯を消してみましょうか」と言う場面がありました。
多くの負傷兵が見捨てられ、出入口をアメリカ軍に塞がれ、火を放たれ、真っ暗闇のなかで沢山の人が亡くなっていきました。
日本の終戦は8月15日ですが、このガマでの終戦は8月22日。それまでここに立てこもっていたのですが、アメリカ軍に収容され、負傷兵も数名が命をとりとめました。
身動きできない真っ暗闇の中で聞こえるのは、わずかに残る負傷兵のうめき声と、自らの傷口をウジが食う音だけだそうです。
そんな断末魔の世界を、なぜ多くの市民が経験しなければならなかったのか。
作家・司馬遼太郎は青年期にこの戦争を経験しました。
18歳で学徒動員されますが、栃木県の地で終戦を迎えます。
召集を受け、一旦は死さえ覚悟した若き日の司馬遼太郎は、戦争が劣勢になってくると理不尽な場面にでくわします。
本土決戦を前にした日本の軍部は、命をかけて国民を守るどころか、最終的に自らの保身を優先するような命令を下すのです。
そのとき彼は「日本人というのは、こんな国民だったのか。いやそうではかったはずだ。戦国時代は、江戸時代は、せめて明治時代以前はそうではなかった・・・・・・」と憤ります。
それから日本が少しでも良くなればと、戦国時代、江戸、幕末の志士を描くことになるのです。

戦争に導いた人達をリーダーとよんで良いのか分かりません。
それでも、国にしろ、組織にしろ、リーダーの判断は、多くの人達に良くも悪くも影響を与えます。
アブチラガマでは、指令室になる予定だったところは、ガマの奥深くで、敵の侵入を防ぐため様々な工夫がされていました。
一方、地元住民があてがわれたスペースは、出口からすぐのところ。
一番奥が駄目、入り口側が良い、というような単純な問題ではありませんが、覚悟と愛情のないリーダーは組織を不幸にします。
ガイドの方の言葉にトゲや恨みは感じませんでした。
しかし、現実に捨て石にされたという事実と記憶が変わることはありません。
美しく、やはり痛い、はじめての沖縄だったのです。