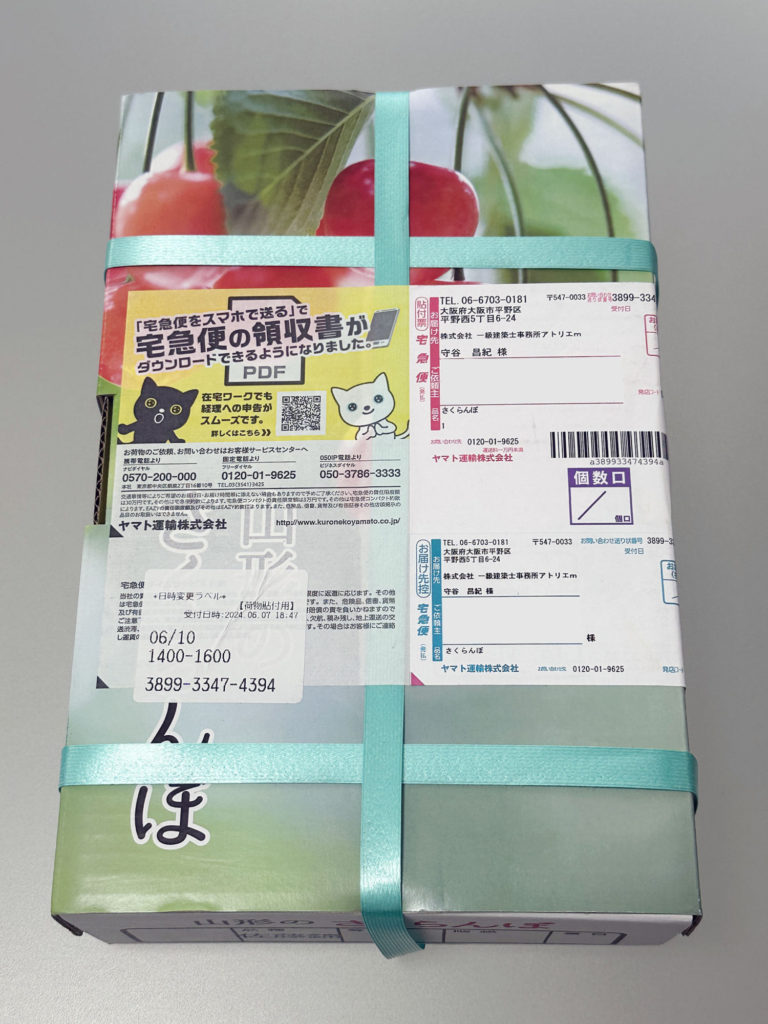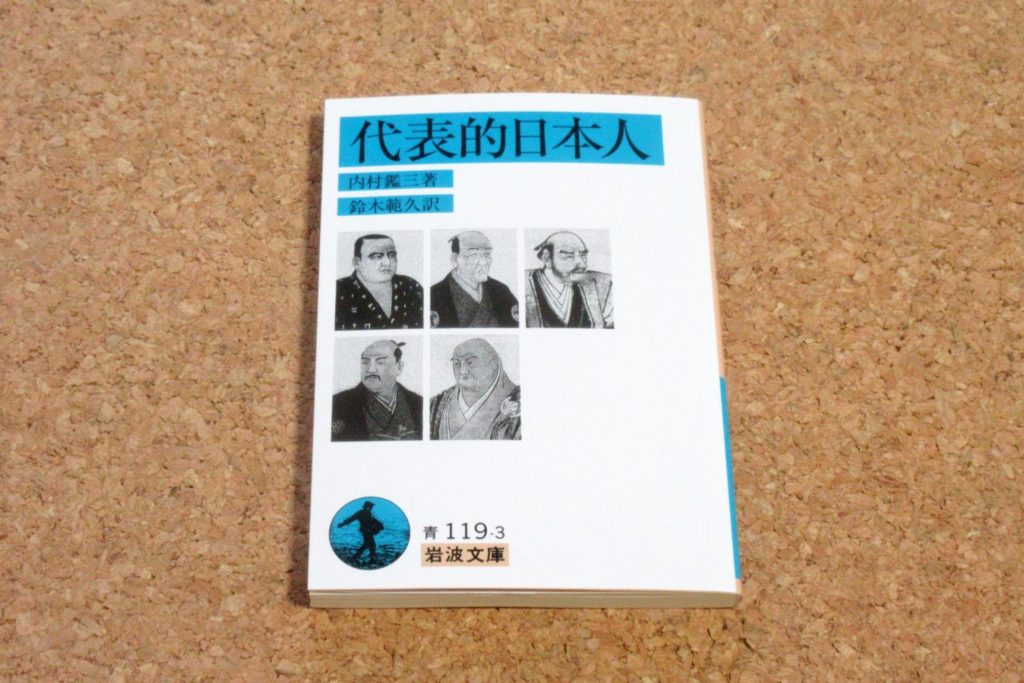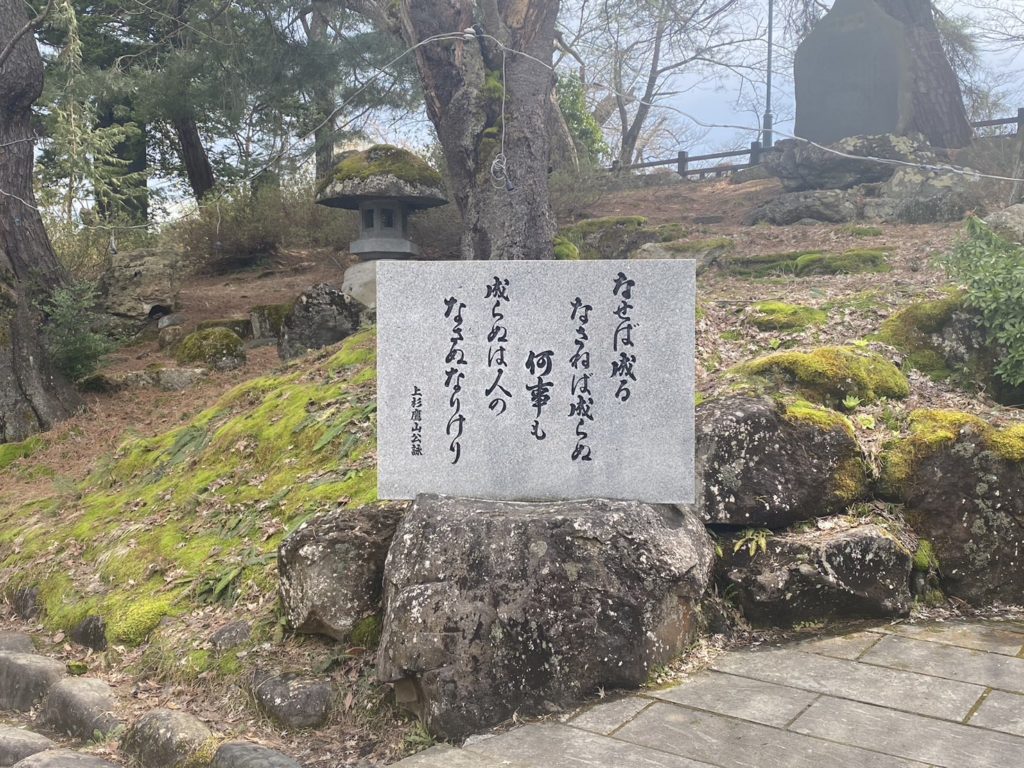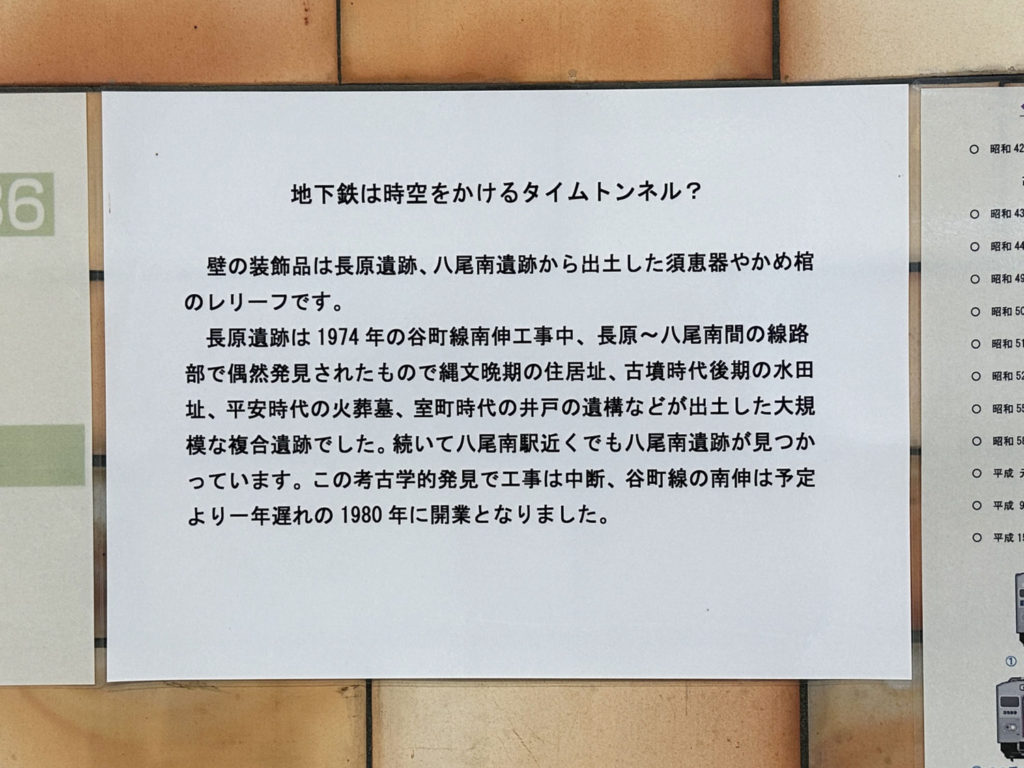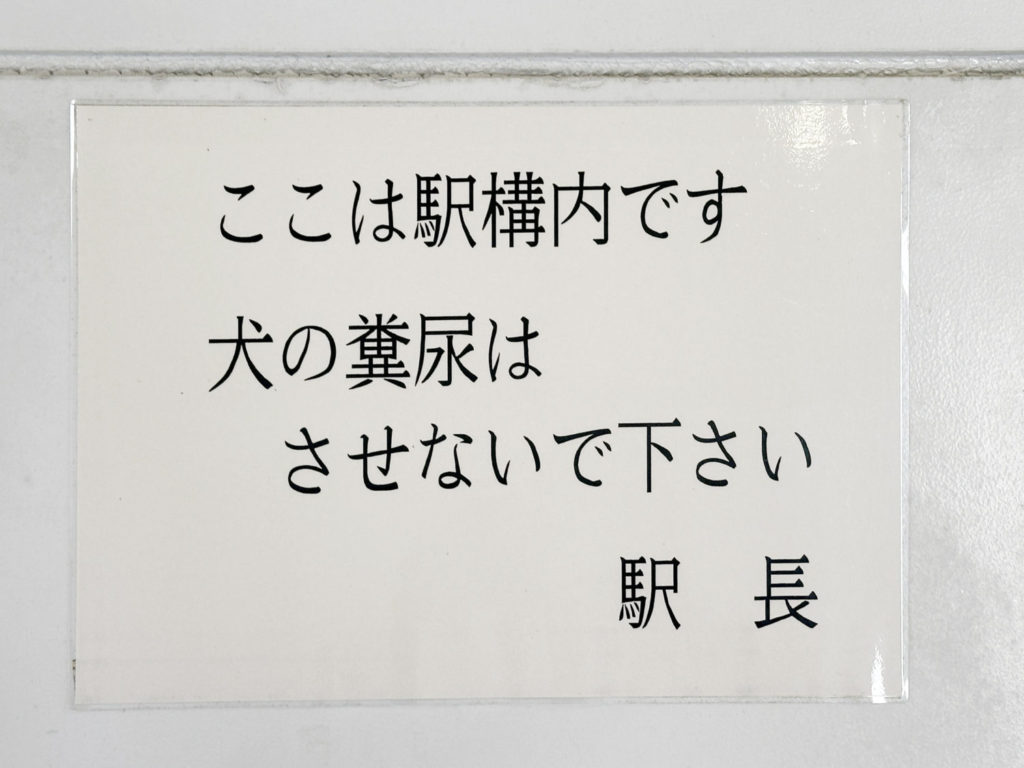先週土曜日、現場からの帰りに梅田を通りました。

夕方になれば、少しだけ暑さがまし。
「釣り道具を補充しておくか」と、釣具屋さんのある大阪駅前第4ビルへ。

阪神百貨店の東側に、かなりの人だかりが。

「梅田涼しくな~れ!」の掛け声と共に打ち水をしていました。
「梅田打ち水大作戦」というイベントのようです。

第4ビルの北側にはパトカーが止まっており、こちらも人が集まっています。
すると、太鼓と笛の祭囃子が聞こえてきました。
先の打ち水も「梅田ゆかた祭2024」の一環のようです。

夕方とは言え、まだまだ暑い中大変だと思いますが、やはり夏は祭りが似合います。

こまめに休憩を挟みながら、ゆっくりと行進して行きます。
「露天神」の文字が見えています。「お初天神」の名前でも知られますが、庶民の楽しみに、神社が果たしてきた役割は非常に大きかったでしょう。
子供が大きくなり、すっかり夏祭りもご無沙汰ですが、たまには屋台のお好み焼きでビールといきたいところです。

平野まで帰ってくると、ちょうど日没でした。

週末、妻と娘は儀父母の家に泊まるというので、買い出しに駅前のスーパーへ。
お惣菜を買ってエコバックに入れ、出張セットのキャスターとカバンの上に。
どんな感じに見えるのだろうと写真を撮ってみました。
相棒のゼロハリバートンのバッグセットも、かなり疲れが見える感じがします。私も同じように見えているかもしれませんが。
今日は大暑。字を見るだけで汗がでてきそうですが、打ち水で対抗したいと思います。
男子ゴルフツアーでショートパンツ解禁のニュースもありました。
身だしなみは大切ですが、コンディションキープはもっと大切。当社でも夏の間は、ショートパンツ解禁にしようかなと思います。
私の一番の強みは、何でも食べられること。夏バテは未経験です。
■■■2月14日『Best of Houzz 2024サービス賞』受賞
■■1月29日発売『日本一わかりやすい 一戸建ての選び方がわかる本2024-25』に「回遊できる家」掲載
◆メディア掲載情報