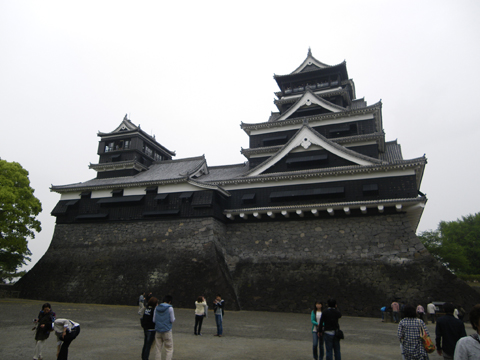前回は、熊本に到着したところまで書きました。
私が担当したのは熊本市の東隣、嘉島町です。災害時の支援活動は以下の流れです。
① 応急危険度判定
② 被害状況調査(1次調査)-外部からの簡易なもの
③ 被害状況調査(2次調査)-内部、外部とも測定等が伴うもの

災害対策本部のある、町民会館。宿泊もここでさせて貰いました。
立派な建物で、山下設計の仕事とのこと。

各班は7名ずつくらいで、嘉島町役場の人をリーダーに、熊本県庁、広島や静岡の町役場の人も参加していました。
市町村はこういった時、互いに助け合うシステムが構築されているようです。
熊本県庁から来ている女性が「普段はデスクワークなので、毎日足がパンパンです」と言っていました。
一日で、大きな会社を2つと住宅の調査をしましたが、暑い中、なかなかの重労働です。
それぞれの班に、日本建築家協会(以下JIA)から参加している私達2人が入ります。
そして、基礎、外壁、屋根、柱などの被害の程度をチームで判定していくのです。

嘉島町から東に益城町や橋が落ちた南阿蘇村があります。
やはり断層が直下に通っている線上に、大きな被害は集中しているとのことでした。
同じ町内でも、被害の集中度が全く違います。

これらの判定で、半壊、全壊と判断された場合、助成金が出るという側面もあり、当然のことながら、責任のある仕事です。
この判断を、役場の方がしているケースが多いのです。

役場の中にも建築士の資格を持っている人がいるのかもしれませんが、やはり専門家が判断するほうが、精度が高いのは間違いありません。
JIAや建築士事務所協会などから、組織的にスピーディーに調査員を派遣するシステムが間違いなく必要だと感じました。
これはJIA九州の人から聞いたのですが、JIAとしては仮に費用が一切でなくても、判定員を派遣すると、早々に結論を出したそうです。
非常時に無報酬でも支援活動をするというのは賛成です。
しかし、それらの詰めがされていないという事実は問題です。

嘉島町に限らないのですが、本当にこのあたりは水が豊かです。
水田の水でさえ、澄み切っています。

川の中でもいたるところから湧き水があります。

そこで泳ぐ人も沢山見かけました。

帰りは、JIA九州の方が、福岡まで帰るので車で送りますよと言ってくれました。
JR博多駅前にあるのは、西日本シティー銀行で1971年、磯崎新の設計です。

博多は2年前の夏に来ましたが、本当に雰囲気のある街です。
まもなく山笠祭りが始まるとのことで、街中に山笠を見かけました。

博多駅前にはかなり大きなものも。
夜の8時過ぎに博多を新幹線で出発しました。
すると8時半頃に熊本で震度3の余震が。またその翌日にも震度4の地震がありました。
私が一人で出来ること等たかがしれています。また、仕事がなければ、ボランティアも不可能です。
その関係に正しい比率などありません。
地震国日本において、建築の専門家でありながら、公には何の貢献も出来ていないという、積年の澱は少しだけ流すことが出来ました。
しかし、地震に終わりなどありません。
豊かな水田、祭りに活気づく若者、そして震度7の地震。いずれもこの日本です。自分に出来る貢献とは……そんな事を考えながら大阪まで帰ってきました。
要請があればすぐに駆けつけられるよう、日々の仕事を頑張るだけだと思っています。